社労士事務所の譲渡相場はいくら?規模別・譲渡価格の目安まとめ
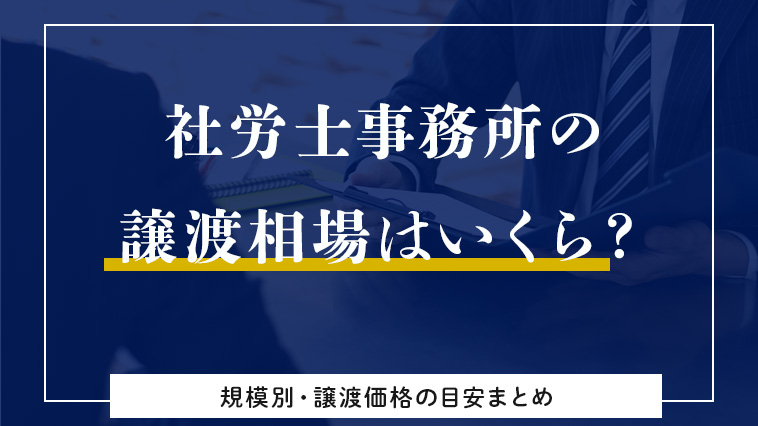
社労士事務所を譲渡したいと考えても、「自分の事務所はいくらで売れるのか」と疑問を抱く方は少なくありません。
適正な価格で譲渡するには、相場を把握し、価格に影響する要因を理解しておくことが必要です。
本記事では、社労士事務所の譲渡相場の目安、価格を左右する主な評価項目、さらに相場を上回る譲渡を実現するための準備や工夫について解説します。
最後まで読むことで、自事務所の強みと課題を整理し、納得のいく譲渡に向けた準備を始められます。
記事の結論
社労士事務所の譲渡相場の目安
譲渡価格の目安を把握する際は、収益性に加えて、事務所のブランド価値がどの程度加味されるかが重要なポイントです。
一般的な算定基準は、「顧問報酬」や「営業利益」の2〜3年分が目安となります。
ただし、事務所の信頼性・専門性・立地・安定性などのブランド価値が高い場合、2〜3倍の価格が付くケースもあります。
▼例
これらはあくまで一般的な目安であり、実際の譲渡価格は個別の条件と交渉によって大きく変動します。
正確な査定を行うためには、専門家のサポートを受けましょう。
社労士事務所の譲渡価格を左右する主な要因
社労士事務所の譲渡相場は一律ではなく、いくつかの条件によって大きく変動します。
相場は、所長や職員の引継ぎ体制、顧問先の安定性、立地やブランド力など、複数の要素が関係します。
譲渡を検討する所長にとって、「自事務所のどこが高く評価されるのか」を知ることは、適正価格を見極めるうえで不可欠です。
ここでは、社労士事務所の譲渡価格を左右する要因を解説します。
自事務所の強みや課題を整理するうえでも、事前に確認しておきましょう。
- 所長や職員の引継ぎ状況
- 顧問先の数と安定性
- 顧問料の水準と契約内容
- 職員体制と属人化の有無
- 事務所の立地とブランド価値
- 財務体質とリスク要因
所長や職員の引継ぎ状況
顧問契約が所長個人との信頼関係に基づく場合、譲渡時の引継ぎ方法によって事務所の価値は大きく変わります。
以下に、社労士事務所の引継ぎ体制ごとの評価傾向を整理しました。
| 引継ぎの形態 | 主なリスク | 買い手の評価 | 譲渡価格への影響 |
|---|---|---|---|
| 所長が完全に退任する場合 | 顧問先が離脱するリスクが高い | 低い | 下がる傾向 |
| 段階的な引継ぎがある場合 | 顧客の不安が軽減され契約継続が期待できる | 高い | 上がる傾向 |
所長が突然退任するケースでは、顧問先の離脱リスクが高まり、譲渡価格が下がる要因となります。
しかし、前所長が半年〜1年ほど残留し段階的に引継ぎに関与する場合、顧客は安心感を持って契約を継続しやすくなります。
最初の3ヶ月は同席、次の3ヶ月は助言役として関与するなど、計画にステップを踏むことが効果的です。
このような体制が整っていれば、買い手側も将来の収益見通しを立てやすくなり、事務所の評価は大きく高まります。
社労士事務所の譲渡を見据える際は、事前に引継ぎ期間や関与の仕方を設計しておくことが重要です。
顧問先の数と安定性
顧問契約は、社労士事務所の収益を支える基盤です。
ただし、評価されるのは契約数の多さだけではありません。
契約の継続性や顧客層の業種バランスも、譲渡価格に影響を与える重要な要素です。
以下に、顧問先に関する主な評価項目と価格への影響を整理しました。
| 評価項目 | 譲渡価格への影響 |
|---|---|
| 顧問先の数 | 顧問契約数が多いほど、高評価につながりやすい |
| 顧問契約の安定性 | 長期契約が多く、安定性が高いほど高評価 |
| 顧客層の業種バランス | 複数業界に分散している場合、リスクが低く高評価 |
固定報酬による長期契約を多く有する事務所は、譲渡後も収益の見通しが立てやすく、買い手からの信頼を得やすくなります。
また、顧問先の業種が建設、IT、医療など複数の業種に分散している場合、不況や法規制変更といった外部要因への耐性が高く、事務所全体の安定性を評価されやすいです。
これらは、買い手が社労士事務所を評価する際の主な基準です。
まずは、自事務所の状況を客観的に見直して強みと弱みを把握することが、買い手の評価を高める第一歩となります。
顧問料の水準と契約内容
顧問料の水準は、事務所の収益性を判断するうえで重要な内部要因のひとつです。
単価の高さや契約内容の質は、将来の収益をどの程度安定して生み出せるかを示します。
以下に、顧問料と契約内容に関する評価ポイントを整理しました。
| 評価項目 | 譲渡価格への影響 |
|---|---|
| 顧問料 | 高額ほど高評価 |
| 契約の安定性 | 長期継続・更新率が高いほどプラス |
| スポット業務実績 | 追加収益が見込めるほどプラス評価 |
顧問料が高く、安定した契約を継続している社労士事務所は、将来的な利益が期待できるため買い手から高評価を得やすいです。
また、就業規則の作成や助成金申請といったスポット案件の実績は、顧問料以外の収益源としてプラス要因になります。
反対に、顧問料が低く件数のみが多い場合には、解約リスクや業務過多による効率低下が懸念され、譲渡価格に悪影響を及ぼす可能性があります。
高値で譲渡するには、「契約単価」「契約の安定性」「追加収益源」の3点を整理し、収益構造を強化しておくことが重要です。
職員体制と属人化の有無
職員体制の強化や業務の標準化は、譲渡時の大きな評価ポイントです。
属人化を解消し、業務の継続性を高める体制を整えることが、譲渡価格の向上につながります。
以下に、職員体制と属人化に関する評価ポイントをまとめました。
| 評価項目 | 譲渡価格への影響 |
|---|---|
| 業務が属人化 | 低評価 (継続性に不安) |
| 業務が分散 | 高評価 (安定性が高い) |
| マニュアル整備 | 高評価 (円滑な運営が可能) |
所長に業務が集中している事務所では、引継ぎ後の運営が不安視され、買い手から低評価を受けやすくなります。
一方で、属人化がある場合でも、事前に業務マニュアルを整備し、引継ぎ計画を具体的に準備しておけば評価が高まります。
職員体制や属人化の有無は、譲渡時に買い手が重視する評価基準のひとつです。
事務所の立地とブランド価値
立地やブランド価値は、価格に直接反映されにくいものの、事務所の存続性や成長性、新規顧客獲得のしやすさといった観点から重視されます。
以下に、立地やブランドに関する主な評価項目と譲渡価格への影響を整理しました。
| 評価ポイント | 譲渡価格への影響 |
|---|---|
| 首都圏・主要都市に立地 | 顧客獲得に有利で高評価 |
| 特定業界への特化 | 差別化により高評価 |
| 地域での信頼 | 安定性が高評価 |
首都圏や主要都市に所在する社労士事務所は、新規顧客獲得や信用面で有利に働き、譲渡価格が上がる傾向があります。
医療、建設、ITなどの特定業界に強みを持つ社労士事務所は、専門性とノウハウによる差別化が明確で、ブランド価値が高く評価されやすい点が特徴です。
また、地域で長年信頼を築いてきた老舗事務所も、安定した顧客基盤がプラス評価となりやすく、地域密着の信頼関係は第三者の新規参入を困難とする競争上の優位性となります。
自事務所の立地条件やブランドの強みを客観的に整理し、譲渡時に明確に伝えることが、価格の引き上げにつながります。
財務体質とリスク要因
借入が少なく財務体質が健全であれば、安定した経営基盤として評価され、譲渡価格のプラス要因です。
反対に、未収金や未払金が多い場合は資金繰りに不安が残り、買い手にとって大きなリスクと見なされ、譲渡価格が下がるおそれがあります。
また、法務・労務上のリスクにも注意が必要です。
行政処分歴や労務トラブルは、事務所の信頼性を損ない、顧問先の離脱や新規獲得の妨げとなって、将来的な収益に悪影響を及ぼす可能性があります。
| リスクの種類 | 具体例 | 譲渡価格への影響 |
|---|---|---|
| 財務体質の弱さ | 顧問料の入金遅延、給与や社会保険料の滞納 | マイナス要因 |
| 法的リスク | 行政から是正指導を受けた経歴 | 信頼性を損なう |
| 労務リスク | 職員から未払い残業代の請求を受けた | 将来収益に悪影響 |
譲渡を検討する際は、財務状況に加え、法的・労務上のリスクも含めて事前に把握し、整理しておくことが重要です。
社労士事務所を高く売るためのポイント
社労士事務所を譲渡する際には、相場を理解するだけでは不十分です。
譲渡を検討する所長が事前に準備や工夫を行えば、譲渡価格を相場以上に高めることが可能です。
実際に高値で譲渡に成功している事務所の多くは、譲渡前に戦略的な取り組みを実施しています。
では、具体的にどのような準備を行えば、譲渡価格を引き上げられるのでしょうか。
ここからは、社労士事務所の譲渡価格を引き上げるための主なポイントを解説します。
- 譲渡のタイミングを逃さない
- 顧問先の安定性を示す
- 属人化を解消する
- 財務状態をクリアにしておく
- M&Aの仲介アドバイザーを活用する
譲渡のタイミングを逃さない
高値での譲渡を実現するには、業績や顧問先の状況が良好な時期を選ぶことが欠かせません。
収益が安定し、顧問先も維持できている状態で譲渡を進めれば、価格交渉を有利に行いやすくなります。
| タイミング | 譲渡価格への影響 |
|---|---|
| 業績が安定している時期 | 最も高値で譲渡しやすい |
| 高齢化・顧問先減少後 | 評価が下がりやすい |
| 業績が下降している時期 | 価格交渉で不利になりやすい |
所長が高齢化し、顧問先が減少してからでは譲渡価格を相場どおりに維持することは困難です。
営業活動の減退や健康上の問題によってサービス品質が低下すると、顧問先の満足度が下がり、契約解約のリスクが高まるためです。
その結果、収益性や継続性に対する評価も低下し、譲渡価格に悪影響を及ぼします。
「まだ売れるかどうか」ではなく「業績が安定しているうちに売るのが最も高値につながる」という視点で、譲渡のタイミングを判断しましょう。
顧問先の安定性を示す
顧問契約の安定性は、単に契約数や更新率の高さだけでは十分といえません。
買い手に安心感を与えるには、社労士事務所の客観的な資料を提示できるよう準備しておくことが必要です。
価格交渉時に整理した顧問リストによって、契約期間や更新履歴を一覧で示すことで、買い手が将来の収益を具体的に把握しやすくなります。
また、顧問先の業種分布を明確に示すことで、リスク分散の効果を伝えられます。
| 準備内容 | 買い手への効果 |
|---|---|
| 顧問リストの整理 | 収益予測が立てやすい |
| 契約更新履歴の提示 | 長期的な安定性を示せる |
| 業種分布の明示 | 複数業種への強みを見せ、リスク分散をアピールできる |
数字や資料で安定性を示せる社労士事務所は、買い手にとって将来の収益をイメージしやすく、高く評価されやすいです。
属人化を解消する
所長のみが担う業務が多い社労士事務所は、買い手にとって不安要素となりやすいです。
事務所を高値で譲渡するためには、属人化をできる限り解消し、誰でも業務を遂行できる体制を整備しておくことが重要です。
| 改善策 | 効果 |
|---|---|
| マニュアル整備 | 業務を標準化し、誰でも同じ品質で遂行可能 |
| 権限委譲 | 所長依存を減らし、引継ぎが容易になる |
| 教育・研修体制 | 職員が自立し、継続性が高まる |
もっとも、小規模の社労士事務所では職員数が限られ、完全な属人化解消が難しい場合もあります。
その場合でも、最低限のマニュアルの用意や所長自身が譲渡後も一定期間フォローに入ることで、買い手の不安を和らげることが可能です。
こうした準備を進めることで、社労士事務所の継続性を示し、譲渡価格を引き上げやすくなります。
財務状態をクリアにしておく
借入が少なく、未収金や未払金がない社労士事務所は、経営基盤が安定していると判断されやすく、買い手から高く評価されます。
一方で、財務内容が不透明な事務所は、買い手にリスクと見なされ、譲渡価格が下がる可能性があります。
不明瞭な会計処理や簿外債務が残っている場合、将来的な資金繰りに対する不安要素となり、買い手は慎重に判断せざるを得なくなります。
| 財務状況 | 買い手の印象 | 譲渡価格への影響 |
|---|---|---|
| 借入が少ない、または返済計画が明瞭 | 健全で安心感がある | プラス評価 |
| 未収金や未払金が多い | 資金繰りに不安を残す | マイナス評価 |
| 会計処理が不透明 | 不正・違法性の疑問を持たれる | 大幅な減額要因 |
財務内容を明確にし、誰にとっても分かりやすい資料を準備しておくことで、買い手は安心して事務所の価値を評価できます。
こうした安心感は信頼につながり、結果として相場を上回る価格での譲渡につながる可能性が高まります。
M&Aの仲介アドバイザーを活用する
社労士事務所を高値で譲渡するには、交渉力や買い手対応の面で専門家のサポートが欠かせません。
M&A仲介会社を利用すれば、幅広い買い手候補にアプローチできるだけでなく、条件交渉をアドバイザーが仲介または代行するため、所長の負担を大きく軽減できます。
また、M&Aの専門知識を持つ第三者が間に入ることで、複雑な交渉や契約条件の調整もスムーズに進めやすいです。
価格だけでなく、顧問先の引継ぎ方法や契約条件などの細部についても、円滑にまとまりやすくなります。
| 譲渡方法 | 特徴と影響 |
|---|---|
| 直接交渉による譲渡 | 所長がすべて対応するため負担が大きく、条件交渉力も弱い 価格が下がりやすい |
| 仲介アドバイザー活用 | 専門家が交渉を代行または仲介するため、条件面も整いやすい 高値でまとまりやすい |
仲介やアドバイザーを活用することは、単に買い手を探すだけでなく、交渉・条件調整・顧客対応を含め、譲渡を有利に進めるための有効な手段です。
社労士事務所の売買にM&A仲介会社を利用するメリット
社労士事務所を高値で、かつ安心して譲渡するには、専門家のサポートが欠かせません。
特に士業M&Aに精通した仲介会社を利用すれば、社労士事務所特有の経営形態や顧問先対応を理解したうえで、適切なマッチングが可能です。
その結果、相場を上回る価格で社労士事務所を譲渡できる可能性が高まります。
ここからは、仲介会社を利用する具体的なメリットを解説します。
- 複数の買い手候補から選べる
- 価格交渉を円滑に進められる
- 譲渡手続きをスムーズに進められる
- 譲渡後のトラブルを防げる
- 士業に精通した専門家によるサポートを受けられる
複数の買い手候補から選べる
自力で買い手を探す場合、候補は1~2者に限られるか、見つからないことも多いのが実情です。
しかし、M&A仲介会社を利用すれば、専門業者としてのネットワークを活用して、10者以上の買い手候補がリストアップされると考えられます。
その中から有力な候補を数者に絞り、優先順位を付けて、M&A仲介会社が順に交渉を打診します。
打診に応じた相手とは秘密保持契約を締結し、交渉を開始する流れです。
| 譲渡方法 | 特徴と結果 |
|---|---|
| 独自サーチ | 簡単には交渉相手が見つからず、見つかっても不利な交渉になりやすい。 |
| M&A仲介会社に委託 | より多くの候補から交渉相手を選別できる。交渉に応じた相手は買収に積極的であり交渉がまとまりやすい。 |
社会保険労務士事務所の買収に積極的な交渉相手である場合、交渉が円滑に進みやすく、有利な条件で合意に至る可能性が高まります。
価格交渉を円滑に進められる
価格交渉は、税理士事務所売却の成否を左右する重要な過程です。
M&A仲介会社に業務委託せず、売り手が自ら直接交渉を行った場合、利害が対立する当事者間での交渉は合意に至りにくい傾向があります。
また、買い手が主導権を握りやすくなるという側面もあります。
M&A仲介会社を活用する場合には、仲介会社が交渉を代行または仲介するため、売り手が直接交渉を行う必要はありません。
仲介会社が交渉に介在することにより、適切な事務所価値の評価に基づく希望条件を客観的かつ論理的に伝えることができ、交渉が円滑に進む可能性が高まります。
| 交渉方法 | 特徴 |
|---|---|
| 直接交渉 | 利害対立による交渉行き詰まりや、買い手有利の展開に懸念 |
| M&A仲介会社に委託 | 専門家が間に入ることで交渉はまとまりやすく、着地点も納得できるものになりやすい |
M&A仲介会社を活用する場合には、手数料が発生します。
一方で、その手数料を惜しむと、「交渉相手が見つからない」「交渉がまとまらない」「不利な条件で売却してしまう」などの事態に陥るおそれがあります。
M&A仲介会社への手数料は、必要な経費と捉え、事務所の売却に臨むことが重要です。
譲渡手続きをスムーズに進められる
社労士事務所の譲渡交渉時には、契約書、顧客リスト、財務資料など多様な書類が必要です。
これらを自力で整えるには多くの手間を要し、不備があれば買い手の信頼を損なうおそれがあります。
M&A仲介会社を利用すれば、必要書類の準備を専門の担当者がサポートするため、売り手の負担を大幅に軽減できるでしょう。
不備や漏れを防ぎながら、予定どおりに手続きを進められます。
| 仲介会社のサポート内容 | 売り手側のメリット |
|---|---|
| 必要書類の準備 | 不備を防ぎ、負担を軽減できる |
| 各プロセスのスケジューリング | スムーズな進行 |
仲介会社のサポートを受けることで、M&A交渉をスムーズに進め、売り手は安心して各プロセスを進められます。
譲渡後のトラブルを防げる
社労士事務所の譲渡後には、顧問先の離脱や職員の退職といったトラブルが起こり得ます。
これらは事業の継続性に直結するため、買い手にとって大きな懸念です。
また、売り手もM&A後、職員の解雇や労働条件の改悪は望みません。
M&A仲介会社が介在すれば、こうしたリスクを事前に洗い出し、契約条件に反映させることが可能です。
売り手側の条件としては「職員の待遇維持」、買い手側の条件としては「表明保証条項による売り手協力義務」を契約に盛り込むことになるでしょう。
なお、職員の大量離職や顧問先の大量離脱などの大幅な表明保証違反が発生した場合、M&Aの取消権や損害賠償請求権が買い手に認められます。
| 立場 | 懸念 | 契約での主な対応・救済(例) |
|---|---|---|
| 売り手 | M&A後に職員の解雇や労働条件の悪化が起きる | 待遇維持条項の設定(一定期間の雇用・賃金・勤務地・勤務条件の維持を明文化) |
| 買い手 | M&A後に職員が離職して事業が回らない | 売り手は事前に職員から転籍承諾を得る+それでも離職が発生した場合の救済条項(取消権/損害賠償請求権) |
| 買い手 | M&A後に顧問契約の解約が起きて業績が悪化 | 売り手は事前に顧問契約継続・引継ぎの承認を顧問先から得る+解約発生時の救済条項(取消権/損害賠償請求権) |
M&A仲介会社のサポートにより、想定されるリスクを事前に条件化しておけば、譲渡後のトラブルを最小限に抑え、安心してM&Aを進められます。
士業に精通した専門家によるサポートを受けられる
社労士事務所の譲渡では、顧問契約の継続や所長依存による属人化リスクなど、士業特有の事情が関係します。
しかし、士業M&Aに特化または支援実績のある仲介会社であれば、専門知識を持つ担当者が事情を踏まえたサポートを行います。
その結果、条件交渉や引継ぎがスムーズに進み、売り手も安心して任せられます。
| 支援内容 | 士業M\&A特化仲介の役割 |
|---|---|
| 事務所価値評価 | 士業事情に応じた事務所価値評価の実施による適切な売却希望額の割り出し |
| 財務・会計サポート | 事務所価値評価に基づき財務・会計上で短期的に改善できる余地があれば、そのアドバイスを行う |
| 顧問契約引継ぎ支援 | 顧問先とトラブルなく契約引継ぎが実現するように折衝時のアドバイスを行う |
士業M&Aに精通した仲介会社を選ぶことで、特有の業務・業界環境に配慮したM&A支援が受けられます。
まとめ|社労士事務所の譲渡は「相場理解」と「準備」が成功のカギ
社労士事務所の譲渡を検討する際は、まず相場の目安を知ることが重要です。
顧問報酬や営業利益の2~3年分を基準に、自事務所の価値を把握しましょう。
そのうえで、高値で譲渡するには事前の準備が欠かせません。
顧問契約の安定性を示す資料の整備、属人化の解消、財務状況の透明化といった取り組みは、譲渡価格に大きく影響するのものです。
そして、M&A専門家のサポートを受けることで、交渉や手続きを円滑に進められます。
特に、士業M&Aに精通した仲介会社を起用すれば、相場を上回る譲渡を実現できる期待を持てます。
社労士事務所の譲渡は特別なことではなく、計画的に準備すれば事務所の未来を築く前向きな選択肢となります。
自事務所の価値を把握するために、まず相場を理解し、準備を始めましょう。
\ 相談料も着手金も無料、まずはお気軽にご相談ください。/
ご相談いただいた内容は、秘密厳守で丁寧に対応させていただきます。