税理士事務所のM&Aの売却相場は?評価ポイントについて解説
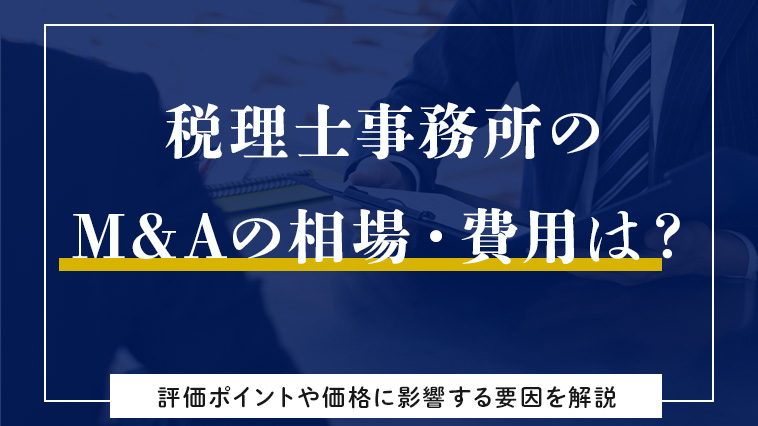
税理士事務所のM&Aを検討する際、最も気になるのが売却価格の相場です。
一般的に、税理士事務所のM&Aによる売却価格は「売上基準(年商の8〜9割)」または「利益基準(営業利益の2〜6年分)」が相場とされています。
ただし、都市部と地方では相場の傾向に違いがあるため、地域ごとの事情も踏まえる必要があります。
したがって、税理士事務所のM&A相場は一律には決まりません。
税理士事務所における顧客基盤の安定性や従業員の定着率、業務効率化の程度などにより、税理士事務所のM&A相場は大きく変動するものです。
本記事では、税理士事務所のM&Aに関し、相場や評価の観点、売買時の注意点についてわかりやすく説明します。
この記事を読めば、税理士事務所のM&A相場を把握できるようになるでしょう。
記事の結論
税理士事務所M&Aの売却価格の相場
税理士事務所のM&Aでは、相場の算定には「売上基準」と「利益基準」の2つが主に用いられます。
税理士業は継続的な顧問契約を中心としたビジネスであり、売上の安定性と利益の再現性が特徴です。
そこで税理士事務所のM&Aにおいては、売上基準であれば年間売上高に一定の倍率を掛けて相場が決まり、利益基準では営業利益に対して複数年分の倍率を掛けて相場とします。

ここでは、税理士事務所のM&A相場における各評価基準の考え方と実務上の注意点について詳しく解説します。
売上基準の場合の相場は年間売上高の「8~9掛け」が一般的
税理士事務所のM&A相場における売上基準とは、年間売上高を基に売却価格を算定する方法です。
税理士事務所のM&Aでは、年間売上高の8~9割程度(0.8〜0.9倍)が相場の目安とされています。
この評価手法が用いられる背景には、月次顧問料や決算料など税理士事務所の定期収入は安定しているという特性があります。
M&Aの買い手にとってもM&A後の収益見通しが立てやすく、投資資金の回収計画を見積もりやすい点も理由の一つです。
ただし、M&Aの現場における実際の相場計算の掛け率には税理士事務所の状況が大きく影響します。
| 相場の掛け率が高くなりやすい要素 | 相場の掛け率が低くなりやすい要素 |
|---|---|
| 従業員数が安定している 買い手が手を加えず運営可能 都市部に立地している | 解約リスクのある顧問先が多い 特定顧客への依存度が高い 短期契約が多い |
相場を検討するうえでの注意すべき点としては、相続案件・スポット契約などによる税理士事務所としての一時的な売上増です。
それらは継続的な収益とは異なるため、M&Aにおける売却価格の相場計算の際に下振れ要因となる可能性があります。

税理士事務所のM&A相場における売上基準は、「事務所の規模」と「収益の安定性」が重視される評価手法であり、安定して売上を維持できるかどうかが重要な要素です。
利益基準の場合の相場は営業利益の「2〜6年分」が目安
税理士事務所のM&A相場における利益基準とは、営業利益を基に複数年分の倍率を掛けて税理士事務所の評価額を算定する方法を指します。
この相場計算は、税理士事務所のM&A後、実際に買い手の手元に残るであろう収益額によって買い手側の投資回収期間の見通しが重視される点が特徴です。
近年、税理士事務所のM&A市場は拡大しており、相場も上昇傾向にあります。
従来のM&Aにおける利益基準の相場計算では「営業利益の2〜3年分」が一般的でしたが、現在は2〜6年分で評価される事例が増えてきました。
税理士事務所のM&A相場における評価の上振れ・下振れには、税理士事務所の体質や事業モデルが大きく影響します。
| 相場が上がりやすい要因 (4〜6年分) | 相場が下がりやすい要因 (2〜3年分) |
|---|---|
| 高単価業務(コンサル・相続支援など)を展開 業務効率化が進んでいる 付加価値サービスが豊富 | 経費過多・人件費比率が高い 一時的な利益変動が大きい 安定収益の構造が乏しい |
このように税理士事務所のM&Aにおける相場計算の利益基準とは、「継続的にどれだけの収益を生み出せるか」に重点を置いた評価手法です。

税理士事務所が安定的かつ高収益な事業モデルを構築しているかどうかが、M&A相場の分岐点となります。
M&A相場における売上基準と利益基準の判断ポイント
税理士事務所のM&A相場における売却価格の評価基準は、税理士事務所の特徴によって適する方法が異なります。
例えば、顧問契約が安定し、解約リスクが低い税理士事務所は、売上基準で相場が上がりやすいです。
一方、業務効率化や付加価値業務により利益率が高い税理士事務所は、利益基準だと相場が上がりやすい傾向があります。
| 相場判断基準 | 適している税理士事務所の特徴 | M&Aの買い手側から見たメリット |
|---|---|---|
| 売上基準 | 顧客との信頼関係が強い 顧問契約の継続率が高い 解約リスクが低い | 安定収益を前提に投資回収計画を立てやすい 将来の売上が予測しやすい |
| 利益基準 | 付加価値業務(相続対策・コンサルなど)の割合が大きい 業務効率化により利益率が高い 経費管理が徹底されている | 実際に手元に残る利益を評価できる 短期間で投資回収しやすい |
税理士事務所のM&Aにおける買い手側からすると、どちらの相場基準を重視するかは、「投資をどれだけ確実かつ早期に回収できるか」という視点に直結します。
安定的な顧問契約はM&A後の売上見通しを立てやすく、利益率の高い税理士事務所は効率的に収益を得られるため、それぞれ異なる魅力が特徴です。
ただし、M&Aでの実務上での実務上では、、相場計算において売上基準か利益基準かを単独で採用することは少なく、両方の基準を組み合わせ、幅を持たせて評価額を算定するのが一般的となっています。
そのため、税理士事務所のM&Aにおける売り手側としては、自事務所が「安定型」か「高収益型」かを把握し、M&A交渉時には両面からの相場を意識することが肝要です。

実際のM&Aにおける相場の目安として、「長期顧問契約の比率が高い税理士事務所は売上基準で評価されやすい」、「利益率や高単価業務の割合が高い税理士事務所は利益基準で評価されやすい」と考えると、自らの税理士事務所の立ち位置を整理しやすくなります。
都市部と地方での相場観の違い
税理士事務所M&Aの相場は、需給バランスや競争環境の違いによって、地域ごとに大きく変動するものです。
都市部では買い手の数が多く競争が激しいため相場は高値がつきやすく、地方では買い手希望者の不足や売り手側税理士事務所の後継者難を背景に相場が抑えられる傾向があります。
このため、地域特性を理解したうえで売り手・買い手ともにM&Aの戦略を立てることが欠かせません。
ここからは、税理士事務所のM&Aにおける都市部と地方での相場観の違いについて詳しく解説します。
都市部(東京・大阪など)は買い手需要が多く相場は高め
都市部では企業数が多く、税理士事務所に対する顧問需要も高いため、買い手希望者が集中しやすい傾向があります。
複数の買い手候補が同一税理士事務所のM&Aに関心を示すことで競争が生じ、結果的に相場は高くなりやすいです。
東京や大阪などの主要都市では売り手税理士事務所数も豊富で、買い手側にとって選択肢が多いことも相場を押し上げる要因となっています。
また、都市部の税理士事務所は上場企業や成長企業との取引が多く、顧客単価が高い傾向にあるのも特徴です。
加えて、人材確保のしやすさや交通アクセスの良さなどの要素も買い手側にとっての魅力となり、M&A後の成長を見据えた投資対象として高く評価されやすい環境が整っています。
| 項目 | 都市部税理士事務所の特徴 |
|---|---|
| 相場水準 | 高め (競争により上振れしやすい) |
| 買い手側の数 | 多い (関心が集中) |
| 売り手の案件数 | 豊富で選択肢が多い |
| 顧客単価 | 高い傾向 (顧客に上場企業・成長企業) |
| 成約スピード | 早い (需要が強く決まりやすい) |

都市部での税理士事務所のM&Aは、売り手側に有利な条件を引き出しやすい一方で、買い手側には競争を勝ち抜くための戦略的な対応が求められる市場といえます。
地方は事業承継ニーズが多いものの買い手不足で相場は低め
地方での税理士事務所のM&Aは、経営者の高齢化と後継者不足が根強く、事業承継ニーズは都市部以上に強くなっています。
しかし、買い手側候補の数は限られており、需給バランスの偏りによって相場は低めになりやすいのが現状です。
それでも、地方の税理士事務所には独自の魅力が存在します。
買い手側にとっては、新規顧客の獲得、営業エリアの拡大、地域人材の確保といった動機があり、条件が合致すればM&Aも成約しやすいでしょう。
また、地方の税理士事務所は、顧客との関係が長期的かつ安定していることも、相場評価におけるプラス要因です。
| 項目 | 地方の税理士事務所の特徴 |
|---|---|
| 相場水準 | 低め (買い手不足で下振れしやすい) |
| 事業承継ニーズ | 経営者の高齢化・後継者不足で強い |
| 買い手の数 | 少ない (候補が限られる) |
| 顧客基盤 | 地域密着型で継続率は高い |
| 買い手の動機 | 営業エリアの拡大 新規顧客の獲得 地域人材の確保 |

地方での税理士事務所のM&Aは、相場が抑えられる傾向がある一方で、適切な買い手とマッチすれば、安定した顧客基盤や人材確保といった強みを活かせる点が特徴です。
税理士事務所M&Aのスキームごとの特徴
税理士事務所のM&Aは、事務所の形態によって選べるスキーム(手法)は異なるものです。
個人が経営する税理士事務所の場合は「事業譲渡」、税理士法人の場合は「事業譲渡」「持分譲渡」「合併」といったM&Aスキームがあり、それぞれ手続きが異なります。
M&Aスキームの違いは、売却価格の相場も左右するため、正しく理解しておくことが重要です。
ここでは、それぞれのM&Aスキームについて詳しく解説します。
個人経営の税理士事務所の場合は「事業譲渡」が中心
法人化されていない個人経営の税理士事務所の場合、M&Aスキームの選択肢は「事業譲渡」のみです。
事業譲渡では、顧問契約、従業員、事務所設備などの資産を個別に承継する形となり、協議によって譲渡・譲受範囲を柔軟に調整できる点が特徴です。
例えば、税理士事務所の経営者が、引退せずに規模を縮小して業務を続けたい場合、一部の顧問契約に限定してM&Aで売却するといった戦略も取れます。
ただし、顧問契約や従業員の雇用契約の承継は、一件ごとに当事者からの同意を得て行う必要があるため、手続きは煩雑です。
また、同意が得られなければ、顧客離脱や従業員の離職といったリスクも伴います。
税理士事務所のM&Aにおける事業譲渡の対価は、譲渡する内容によって金額が変動するため、相場はケースバイケースです。
| 引継ぐ対象 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| 顧問契約 | 買い手・売り手の協議により承継対象契約を選別できる | 顧客ごとに同意が必要 解約リスクが発生 |
| 従業員 | 人材の選別も可能 | 買い手は雇用契約を新たに締結する必要があり離職リスクがある |
| 設備・資産 | 承継対象の資産を識別できる | 買い手・売り手間の合意が必要 |
| 全体の特徴 | 柔軟な契約設計が可能 | 手続きが煩雑 消費税対象資産を承継する買い手側には消費税が発生 |

税理士事務所のM&Aにおける売り手は、顧客や従業員に対して丁寧な説明を行うこと、一方の買い手は承継リスクを見越した計画を立てることが重要です。
税理士法人の場合は「持分譲渡」や「合併」が可能
法人化した税理士事務所、すなわち税理士法人では、事業譲渡以外のM&Aスキームとして、株式に相当する「持分」を譲渡する方法(持分譲渡)や、法人同士が合併する方法も選択できます。
持分譲渡は、売り手側税理士事務所の代表社員(株式会社の取締役や代表取締役に相当)が持つ出資持分を別の税理士に売買するM&A取引です。
出資持分を所有する代表社員には出資額に応じた経営権があるため、持分をM&Aで取得した買い手税理士はその経営権を手にすることになります。
なお、税理士法人は最低でも2名の代表社員を置くことが定められているため、中小企業のように経営者が全株式(全経営権)は持てません。
持分譲渡は、外部または内部の税理士がこれまでの代表社員に代わって、売り手側税理士事務所の経営陣に加わるM&Aスキームです。
一方、合併は複数の税理士法人を1つに統合するM&Aスキームです。
売り手側の税理士事務所は消滅し、買い手側税理士事務所が存続します。
税理士事務所の合併では、スケールメリットの追求や人材活用の効率化が可能です。
ただし、M&A後の経営統合には時間と調整が必要であり、それぞれの税理士事務所の組織文化の相違や業務フロー統一の負担には注意する必要があります。
合併によるM&Aの場合、売り手側税理士事務所の経営者は引退せず、買い手側税理士事務所に残ることも可能です。
| M&Aスキーム | 特徴 | メリット | デメリット |
|---|---|---|---|
| 持分譲渡 | 出資持分の売買によって経営権を買い手に移動 | 経営者・経営陣が交代するだけで組織に変更はないため顧客・従業員への影響が少ない | 持分比率による経営権調整が必要 経営方針が変わる可能性 |
| 合併 | 複数の法人を1つに統合 | スケールメリットが得られる 人材・ノウハウの取得 | 組織文化や業務フローの相違により摩擦が生じやすい 売り手税理士事務所を丸ごと取得するため相場は高め 包括承継であるため買い手は簿外債務を引継ぐ可能性がある 経営統合には手間がかかる |

税理士法人のM&Aでは、スリム化を図るなら事業譲渡、スムーズな承継を重視するなら持分譲渡、規模拡大や効率化を目的とするなら合併といったような、目的に応じたM&Aスキームの選択が重要です。
税理士事務所M&Aのスキーム態様
税理士事務所のM&Aにおける各M&Aスキームの内容を分類すると以下のようになります。
| M&Aスキーム | M&A対象 | 売り手 | 買い手 | 相場 | 手続きの特徴 |
|---|---|---|---|---|---|
| 事業譲渡 | 事業 | 個人 | 個人 | 譲渡される事業の規模に応じて可変 | 個別承継であり煩雑 |
| 個人 | 法人 | ||||
| 法人 | 個人 | ||||
| 法人 | 法人 | ||||
| 持分譲渡 | 代表社員個人の持分 | 対象法人の代表社員個人 | 個人 | 持分の金額に応じて可変 | 個人間の売買取引のみであり簡易的 |
| 合併 | 代表社員の全持分 | 対象法人の代表社員全員 | 法人 | 対象法人の規模に応じて可変 | M&A手続き以外に売り手は廃業手続き、買い手は経営統合計画策定と実行が伴う |
事業譲渡の売り手個人とは個人経営の税理士事務所、事業譲渡と持分譲渡の買い手個人とは未開業の税理士または税理士事務所のことです。
未開業の税理士の場合、M&Aで譲渡された事業を基に税理士事務所を開業します。
税理士事務所のM&Aにおける事業とは顧問契約を指すため、顧問契約の量・内容が相場を上下させます。

税理士事務所のM&Aにおける買い手にとって懸念事項である簿外債務ですが、M&Aスキームに事業譲渡を選択することで回避できます。
税理士事務所のM&Aにおける評価のポイントと売却価格相場に影響する要因
税理士事務所のM&Aにおける売却価格相場の算定は、単に売上や利益の数字だけで決まるわけではありません。
買い手側は「将来にわたって安定収益を確保できるか」「どの程度の成長余地があるか」といった視点から売り手側税理士事務所の総合力を見極めます。
そのため、どの要素が高い評価を得られやすいのかを理解しておくことは、売却準備の優先順位を整理するうえで不可欠です。
ここでは、税理士事務所のM&Aにおける具体的な評価ポイントを詳しく解説します。
安定した顧問契約と契約期間の長さ
税理士事務所における長期の顧問契約や高い更新率は、M&Aの買い手側に安心感を与える要因となり、評価を押し上げます。
顧問契約が安定していれば、M&A後の収益見通しを立てやすく、買い手が投資を回収できないリスクも小さくなるためです。
3年以上の長期顧問契約や自動更新契約が多い税理士事務所は、M&Aで高く評価されやすい傾向にあります。
反対に、短期顧問契約や単発契約が中心で顧客の入れ替わりが多い税理士事務所は、顧客離脱リスクが高く、売却価格にマイナスの影響が及びやすいです。
買い手側は、更新条件や解約条項など顧問契約の内容を詳細に確認し、安定性を評価します。
また、月次顧問料の回収状況や未収金の有無も、信頼性を示す重要な要素です。
| 評価項目 | 高評価となる状態 | 低評価となる状態 | 買い手側からの見方 |
|---|---|---|---|
| 契約期間 | 3年以上の長期契約が多い 自動更新になっている | 短期契約(1年未満)や単発契約が多い 自動更新になっていない | 長期契約は安心材料 短期契約中心は顧客離脱リスク大 |
| 更新率・解約率 | 更新率90%以上 解約件数が少ない | 顧客の入れ替わりが激しい 解約率が高い | 安定性の高さは売却価格に直結 |
| 顧問料の安定性 | 毎月一定額の入金で安定している 未収金が少ない | 売上高の波が大きい 未収金が目立つ | 投資回収の確実性を判断する基準になる |
| 顧客との関係性 | 長期的な信頼関係が構築されている 紹介による契約継続が多い | 浅い関係性が多く、価格競争により低額で契約しているケースが目立つ | 継続率の高さは「引継ぎ後の安心感」に直結 |

税理士事務所のM&Aによる売却を検討する際には、契約書の更新条項における自動更新の有無を整理し、安定性を裏付ける資料を準備しておくことが有効です。
優良顧客・高収益クライアントの割合
税理士事務所における売上の安定性は、単なる顧客数ではなく「顧客の質」に大きく左右されます。
相続税申告、事業承継コンサル、資産税、国際税務、M&Aアドバイザリーなどの高額業務が一定割合を占める税理士事務所は、収益性が高く評価されやすい傾向です。
また、上場企業や安定した中堅企業を顧客として抱える税理士事務所は、景気変動への耐性があると判断されます。
一方、売上の大部分を少数の顧客に依存している税理士事務所は、リスクが高いと判断されて、評価は下がりがちです。
| 評価観点 | 高評価につながる特徴 | 評価が下がる要因 |
|---|---|---|
| 顧客の質 | 高額業務(相続税・事業承継・資産税・国際税務など)が一定割合を占める | 低額業務に依存 |
| 収益基盤 | 上場企業や安定中堅企業が多い | 零細企業中心で景気変動に弱い |
| 依存リスク | 上位顧客の売上比率が10〜15%以内に分散 | 特定顧客が売上の大部分を占める |
| 契約の継続性 | 長期契約や安定した取引実績 | 短期契約が多く解約率が高い |

税理士事務所における売上高構成の理想は、売上上位顧客であっても全体の10〜15%以内に収まることです。また、顧客の業種、規模、地域が分散しているほど、安定性が高いと判断されます。
従業員の在籍年数や定着率
経験豊富で勤続年数の長い従業員が多い税理士事務所は、M&A承継後の引継ぎが円滑に進むと評価されます。
その理由は、従業員の定着率が高い税理士事務所ほど顧客対応の安定性が維持されていると判断され、売却価格の向上につながるためです。
税理士資格を持つ従業員や実務経験豊富なベテランが在籍している事務所の場合、買い手側は安心して業務を承継できます。
離職率が高い税理士事務所は「M&A後に業務が停滞するリスクがある」として低評価を受けやすく、人材採用や教育コストの増加も懸念材料です。
| 評価観点 | プラス評価の目安 | マイナス評価の要因 |
|---|---|---|
| 平均勤続年数 | 5年以上が目安、経験豊富で引継ぎが円滑に進む | 勤続年数が短く、担当者が頻繁に入れ替わっている |
| 離職率 | 年5%未満なら安定と評価されやすい | 離職率が高く、のちの人員不足リスクあり |
| 資格保有者の在籍 | 税理士・科目合格者が在籍し、専門性を担保 | 資格者が少なく、特定人物への業務依存度が高い |
| 年齢・構成のバランス | ベテランと若手がバランス良く在籍し将来性も評価 | 高齢化が進み、後継育成の体制が弱い |

M&Aの買い手は従業員も重視するため、ベテラン、資格者、若手のバランスが整っている税理士事務所は、安定性と将来性の両面で高く評価されます。
業務効率化とDX化の導入
税理士事務所において、クラウド会計ソフト、ペーパーレス化、RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)の導入は、効率的に利益を生み出せる体制を示す要因です。
DX化が進んでいる税理士事務所は買い手側にとって追加投資の負担が少なく、M&A後、直ちに利益を確保しやすいため、高く評価されます。
紙ベースの作業やアナログ業務に依存している税理士事務所は、システム導入費用や従業員の再教育などのコストが必要となり、評価額は低下する傾向です。
| 評価観点 | プラス評価の要素 | マイナス評価の要素 |
|---|---|---|
| 会計ソフト | クラウド型を導入し自動仕訳や連携機能を活用 | インストール型や手入力に依存 |
| ペーパーレス化 | 電子申告・データの電子保存を徹底し紙資料の削減が進んでいる | 紙資料中心で保管コストがかかり検索効率も悪い |
| 業務自動化(RPA) | 定型業務を自動化し省人化が進んでいる | 手作業に依存し人的ミスや工数が多い |
| 顧客対応 | Web面談・クラウド共有を活用し利便性が高い | 対面や郵送中心で時間・コスト負担が大きい |
| 導入コストの見込み | 追加投資がほぼ不要でM&A後、直ちに収益化が可能 | 大規模なシステム投資や教育コストが必要となる |

税理士事務所における業務マニュアルの電子化や顧客とのやり取りのデジタル化の有無は、M&A後の経営効率に直結するため、重要なチェックポイントです。
サービス多角化による付加価値(相続・コンサル・人事労務など)
税務顧問に加えて、相続対策、事業承継コンサル、人事労務支援を提供する税理士事務所は、収益源が多角化しているため、高く評価されやすいです。
単一業務に依存せず、景気変動や顧客流出リスクを分散できる点が大きな強みとされます。
高額で需要が拡大している分野を扱う税理士事務所は、「将来の成長余地がある」として相場が上昇しやすい傾向です。
付加価値サービスを備える税理士事務所は、M&Aの買い手にとって「即戦力となる新規事業部門」の獲得を意味します。
| サービス種別 | 評価されるポイント | 相場への影響 |
|---|---|---|
| 相続・資産税業務 | 高額・高収益、需要拡大中 | 高評価になりやすい |
| 事業承継・組織再編コンサル | 経営層との強固な関係性、専門性 | 成長余地があり相場は上昇 |
| 人事労務支援 | 継続的な顧客接点、付加価値サービス | 安定収益を評価 |
| 経営コンサル・国際税務 | 顧客基盤の拡大、新市場への対応 | 差別化要因となる |

税理士事務所のM&Aにおいて、売却準備の段階で提供サービスの幅や実績を整理しておくことは、価格相場を高める上で重要な要素です。
税理士事務所を売却検討する側が注意すべきポイント
税理士事務所のM&Aによる売却を有利に進めるためには、場当たり的に進めるのではなく、事前の体制整備とリスク対策が不可欠です。
買い手側が注目するのは、収益の安定性や将来の成長余地であり、それを踏まえて準備するかどうかによって、評価額や交渉の進展具合は大きく変わります。
売却を検討する税理士事務所が取り組むべき事項は、「準備」「改善」「節税」の3つの観点です。
ここでは、それぞれの具体的なポイントを整理し、どのように売却の成功につなげるかを解説します。
早めの準備で顧客・従業員の流出を防ぐ
M&Aの準備不足は、顧客離脱や従業員退職など、大きな損失につながるおそれがあり注意すべきポイントです。
早期に準備を開始することで、情報管理や引継ぎ体制を整備し、安定した承継を実現しやすくなります。
重要なのは、顧客、従業員に対し、彼らの立場を理解したうえで丁寧にM&Aの説明をすることです。
説明の準備を早い段階から進めておくことで、顧客や従業員に不安を与えることなくM&Aを進められるでしょう。
なお、M&Aでは、交渉開始時に売り手・買い手間で秘密保持契約(NDA)を締結するのが鉄則です。
これに違反すると損害賠償請求を受けたり、M&A交渉が破談になったりする可能性があります。
したがって、顧客や従業員にM&Aの説明をするタイミングは、秘密保持契約に違反しない時期を見計らうことが肝要です。
| 観点 | 準備不足の場合のリスク | 早期準備を行った場合の効果 |
|---|---|---|
| 顧客対応 | 不信感が生じ解約に至る可能性がある | 十分な説明を行うことでM&Aへの理解を得られる |
| 職員対応 | 不安や心配が生じると退職者が出る可能性がある | |
| 承継手続き | 契約・引継ぎが慌ただしくなる | 計画的に進められ、顧客・従業員双方の負担を最小限に抑えられる |

税理士事務所のM&A交渉では、従業員の待遇維持を制約条件に加えることで、M&A後の安定した体制移行が実現します。
高値売却のカギは業務効率化と顧客基盤の強化
税理士事務所においてM&Aの実施までに業務効率化やDX化を進めることは、買い手側から「M&A後すぐに収益を上げられる事務所」と評価されやすくなります。
クラウド会計ソフトの導入、ペーパーレス化、業務マニュアルの整備は、短期間でも成果が確認しやすく、投資効果が売却価格に直結しやすい施策です。
また、顧客基盤の強化も重要です。
特定の大口顧客に依存している場合はリスク要因となりますが、幅広い顧客層を確保し、相続、事業承継、人事労務などの高付加価値サービスを提供している税理士事務所は、将来性が高いと判断されます。
すなわち、税理士事務所をM&Aにおいて高値で売却する条件は「効率性」と「安定性」を兼ね備えることです。
| 観点 | 改善の方向性 | 買い手側からの評価 |
|---|---|---|
| 業務効率化・DX化 | クラウド会計、RPA、マニュアル整備、ペーパーレス化 | 追加投資が不要 |
| 顧客基盤 | 顧客の分散、契約更新率の向上、高付加価値サービスの提供 | 安定性・将来性が高く、リスク分散が図られている税理士事務所と評価される |

税理士事務所において効率化と顧客基盤の両面を整えておくことで、M&Aの買い手側に「安心して投資できる」と認識させ、結果として高値売却につながります。
税理士事務所を買収検討する側が押さえておきたいポイント
M&Aにおいて税理士事務所を買収する際に、価格のみで判断すると、M&A後に想定外のリスクを抱えるおそれがあります。
買い手側が留意すべき事項は、投資回収の見通し、顧客および人材の流出リスク、体制の確保ならびに統合プロセスです。
これらを総合的に評価することにより、初めて安心して投資できるM&Aといえます。
以下では、税理士事務所のM&Aによる買収を成功させるために重視すべき観点を解説します。
投資回収期間の見込みを判断する
M&Aの成否は、買収金額を何年で回収できるかによって大きく左右されるものです。
一般的にM&Aの投資回収期間は、中小企業が2年以内、大企業が行う大型投資で5~7年程度といわれています。
例えば、年間営業利益が1,000万円の税理士事務所を2,000万円で買収した場合、単純計算では2年で投資回収が可能です。
しかし、実際には統合コスト、人件費の増加や顧客離脱を考慮する必要があります。
このため、複数のシナリオを想定し、M&A後の投資回収シミュレーションを行うことが重要です。
| シナリオ | 前提条件例 | 投資回収期間の想定 |
|---|---|---|
| 最良ケース | 顧客増加とシナジー効果が発揮され 利益2,000万円/年 | 1年 |
| 標準ケース | 現状維持で 利益1,000万円/年 | 2年 |
| 最悪ケース | 顧客離脱とコスト増により 利益700万円/年 | 3年超 |

税理士事務所のM&Aにおいては、投資回収期間を短縮できる余地があるか、またリスクが許容範囲内に収まるかを精査することにより、買収判断の精度が高まります。
デューデリジェンスでM&A後のリスクを洗い出す
税理士事務所のM&Aだけでなく一般企業のM&Aにおいても、簿外債務はM&A後に発覚するとダメージが大きいリスクとされています。
そのため、事前に以下の簿外債務の有無および規模をデューデリジェンスで調査しましょう。
簿外債務の具体例
訴訟リスクを調査するのが法務デューデリジェンス、それ以外の簿外債務を調査するのが財務デューデリジェンスです。
簿外債務は帳簿(貸借対照表)に載っていない債務であり、税理士事務所といえども、売り手側が見落としている可能性があります。

法務デューデリジェンスでは弁護士、財務デューデリジェンスでは公認会計士といったように、それぞれ専門家へ依頼して調査するのが一般的です。
人材の確保状況と顧客基盤の安定性を評価する
税理士事務所の評価において、最も重視されるのは「人材」と「顧客基盤」です。
従業員が長期的に定着している税理士事務所は、顧客との関係が途切れにくく、M&A後も円滑に業務を引継げます。
税理士資格者や実務経験が豊富な人材が一定数在籍している場合、専門性の担保につながり、高い評価を受けやすいです。
離職率が高い税理士事務所は、M&A後に業務が停滞するリスクや追加採用コストが懸念材料となります。
| 評価対象 | 確認項目 | 高評価のポイント | リスク要因 |
|---|---|---|---|
| 人材 | 離職率・定着率 | 長期勤務者が多く、税理士資格者も在籍 | 高い離職率や資格者不足 |
| 顧客基盤 | 売上構成・解約率 | 顧客層が分散し、大口依存が少ない | 特定顧客依存、解約率が高い |
| 将来性 | 顧客年齢層 | 若手経営者や成長企業が多い | 高齢顧客ばかり、承継リスク大 |

税理士事務所のM&Aにおいて、人材は「安定した業務継続力」を、顧客基盤は「収益の持続性」を示す重要な要素です。
両面でバランスの取れた税理士事務所ほど、買収後の安心感を持てます。
買収後の経営統合プロセス(PMI)で起こりやすい課題と対応策を知る
税理士事務所のM&Aにおいて買収によるシナジー効果を実現させるためには、統合初期の90日から180日以内に「人・システム・業務」を安定させることが必要です。
PMI(ポスト・マージャー・インテグレーション、M&A後の経営統合プロセス)を怠れば、買収効果が失われ、混乱や顧客離脱につながります。
税理士事務所は業務の属人性が高いため、円滑な経営統合には事前準備と段階的対応が不可欠です。
以下にM&A後のPMIにおける主な課題と対応策をまとめました。
| 課題 | 内容 | リスク | 主な対応策 |
|---|---|---|---|
| 従業員の不安 | 雇用条件や評価制度の変化による不安 | 離職、士気低下、情報流出 | 統合前から説明会を実施し、信頼形成を図る |
| システム統合 | 会計・顧客管理システムの相違 | データ不整合、業務停止 | 段階的移行を計画し、並行稼働期間を設ける |
| 業務フローの違い | 手順や役割分担の相違による混乱 | 顧客対応の質低下、内部対立 | 現行フローを比較し、統合後の手順を共有 |
| 顧客引き継ぎ | 関係構築の不備で信頼を損なう | 顧客離脱、売上減少 | 引継ぎ方法を明示し、面談を行う |
| 組織文化の違い | 意思決定や働き方の価値観の差異 | 組織分裂、摩擦の発生 | 共通行動指針を定め、早期の融和を促す |
いずれかの課題でも対応が遅れれば、経営統合全体に影響します。
したがって、買収検討段階から経営統合計画を策定し、次の事項を計画書に明記しておくことが重要です。

税理士事務所のM&Aにおける買い手にとって、買収してM&Aが完了ではありません。PMIを成功させて初めてM&Aが成功といえます。技術や制度の統合に加え、人材や組織文化への配慮を欠かさない経営統合計画が求められます。
税理士事務所の売買でM&A仲介会社を利用する際の費用相場
税理士事務所のM&Aでは、M&A仲介会社を利用するのが一般的です。
M&A仲介業界の手数料には法令による定めがなく、仲介会社ごとに料金体系はことなります。
近年では、成功報酬(詳細は後述)のみの完全成功報酬制を採用するM&A仲介会社が増えています。
以下に、M&A仲介会社に業務委託した場合に発生する可能性のある各種手数料の概要と相場をまとめました。
| 手数料名 | 概要 | 相場 |
|---|---|---|
| 着手金 | M&A仲介会社との業務委託契約締結時に支払う | 0〜50万円程度 |
| リテイナーフィー | 業務委託契約締結時からM&Aが成約するまで毎月支払う顧問料 | 月額10〜30万円程度 |
| 中間金 | M&A当事者間で基本合意書を締結した際に支払う。成功報酬の一部前払い扱いが多い | 50〜100万円程度 |
| デューデリジェンス費 | デューデリジェンスを委託する士業や専門家に支払う手数料 | 数十万円~200万円程度 |
| 成功報酬 | M&A成約時に支払う | レーマン方式などにより算定 |
デューデリジェンスとは、買い手が売り手企業の事業や財務、法務、労務面のリスクを事前に調査する手続きのことです。
会計・税務・法務・労務の専門家が実施し、M&Aの最終判断に重要な役割を果たします。
デューデリジェンス費は全額、買い手側が負担するものです。
完全成功報酬制以外のM&A仲介会社では、上記手数料全てが発生する場合もあれば、着手金のみ・中間金のみのケースもあります。
また、着手金、リテイナーフィー、中間金を成功報酬の前払い扱いとし、成功報酬支払時に差し引き計算するM&A仲介会社もあります。
したがって、M&A仲介会社との業務委託契約時には料金体系の確認が欠かせません。
完全成功報酬制以外のM&A仲介会社と業務委託契約を締結する際の注意点は、M&A成約前に支払う着手金、リテイナーフィー、中間金、デューデリジェンス費は、M&Aが破談になった場合、返金されないことです。

完全成功報酬制を掲げているM&A仲介会社でも、完全成功報酬制は売り手のみで、買い手には中間金も発生といったケースもあり、細かな料金体系の確認が不可欠です。
M&A仲介会社の成功報酬計算におけるレーマン方式とは
M&A仲介会社で用いられているレーマン方式とは、「成功報酬(仲介手数料)」を計算するときに使う方法の一つです。
取引金額をいくつかの金額帯に区切り、それぞれの金額帯に異なるパーセンテージ(料率)をかけて報酬を計算します。
同じ取引金額でも「どこまでを計算の基準にするか(=計算基準額)」によって報酬額は変わります。この基準の考え方はM&A仲介会社ごとに異なり、主に4つのパターンに分かれています。
M&A対価
売り手が買い手から受け取る「M&A対価」そのものを基準とする最もシンプルで分かりやすい基準額。4種の基準額中、最も額が低いものです。
経営者受取額
税理士事務所経営者が事務所に運営資金を貸し付けている場合、M&A後、買い手からその返済を受けます。つまり、「M&A対価+返済金=経営者受取額」としてレーマン方式の計算基準額とします。M&A対価だけよりも基準額は高くなります。
企業価値
企業価値評価における企業価値の定義は「株式価値+有利子負債」です。株式価値とは一般の企業のM&Aでは株式譲渡の場合の対価とほぼ同義です。有利子負債とは借入金や社債などの合計額が該当します。端的に言えば税理士事務所経営者およびそれ以外からの利子付き借金の総額です。したがって、経営者受取額よりも企業価値の方が高額となります。
移動総資産
レーマン方式の計算基準額としては最も高額であり、成功報酬額もそれに比例します。株式価値に、有利子負債だけでなく、利子のない負債である買掛金や未払金などを含む負債総額を加えた額を移動総資産といいます。
なお、M&A仲介会社の成功報酬は、レーマン方式の基準額や手数料率、金額帯の区分が会社ごとに異なります。

そのため、契約前に見積書の提示を求めれば、各社の違いを比較しやすくなります。
税理士事務所M&Aを仲介会社に依頼する際の選び方
税理士事務所のM&Aは、専門的な知識や高度な交渉力が求められるため、仲介会社の支援を受けて進めるのが一般的です。
しかし、仲介会社の選定を誤ると、売却価格が相場より低くなる、交渉が長期化する、条件面で不利になるといったリスクが生じるおそれがあります。
適切な仲介会社を見極めるうえで重視すべきポイントは、「実績」「手数料」「ネットワーク」の3点です。
これらを総合的に比較・評価することで、自事務所にとって最適なM&A仲介会社を選定しやすくなります。
ここでは、税理士事務所M&Aを仲介会社に依頼する際の選び方を詳しく解説します。
士業M&Aの実績が豊富な仲介会社を選ぶ
M&Aを円滑に進めるためには、実績豊富な仲介会社を選ぶことが不可欠です。
税理士事務所のM&Aでは、顧問契約の継承や資格に関する制約、従業員や顧客との関係性など、他業種にはない専門的な配慮が求められます。
そのため、「過去の成約件数」だけでなく、どのような業種・規模のM&A案件に対応してきたか、士業のM&Aに特化したノウハウを有しているかが、仲介会社を見極めるうえでの重要な判断材料です。
以下に、実績確認時に注目すべき主なポイントをまとめました。
| 項目 | 着眼点 | 理由・確認すべきこと |
|---|---|---|
| 成約件数 | 過去にどの程度の数のM&Aを仲介してきたか | 数が多ければ一定の信頼はおける |
| 士業M&Aの経験 | 税理士事務所のM&Aを仲介した実績があるか | 業界特有の規制や商慣習を理解していないと適切な対応が難しい |
| 平均成約スピード | 過去の成約実績において要した期間を確認する | 成約スピードが速い=交渉力が高いと考えられる |

その他にもM&A仲介会社選びの着眼点として、特定の地域に強みがあるか、あるいは全国対応のような広域をカバーしているかというものもあります。
弁護士・公認会計士など専門士業とのネットワークがあるかを確認する
M&Aの各プロセスには、企業価値評価・デューデリジェンス・契約書作成のように、弁護士・公認会計士・税理士・社労士などの専門家との連携が必要になる場面があります。
したがって、外部の士業事務所との連携関係を持っているM&A仲介会社を選ぶべきです。
昨今では、弁護士や公認会計士などが在籍しているM&A仲介会社もあります。
また、法律事務所や会計事務所自体がM&A仲介業を行っているケースもあり、選択肢は広がってきました。
| 専門家連携のポイント | 関与する専門士業 | 対応内容・効果 |
|---|---|---|
| 契約書の作成・確認 | 弁護士 | トラブル回避の契約設計 リスク条項の排除 法的整合性の確保 |
| 税務リスクの検証 | 税理士、公認会計士 | 譲渡所得税、消費税、法人税、繰延税金の処理 |
| 法務・資格確認対応 | 弁護士 | 独占業務・資格要件の遵守確認 免許・登録制限の洗い出し |
| デューデリジェンス | 税理士、公認会計士、弁護士、社労士、IT専門家 | 財務・税務・法務・労務・ITシステムなどのリスク精査と可視化 |
| PMI支援 | 公認会計士、社労士、IT専門家、ファイナンシャルプランナーなど | M&A後の経営統合サポート |

これらの連携体制は、M&A仲介会社の公式サイトや初回相談時に確認しておくことが重要です。
税理士事務所M&Aの進め方と具体的な流れ
税理士事務所のM&Aは、いくつものプロセスを経て進められます。
M&Aの各プロセスは、専門的な知見が求められるため、M&A仲介会社のような専門家のサポートが欠かせません
ここでは、税理士事務所のM&Aにおける売り手側の一般的な進行フローをM&A仲介会社に業務委託した前提で説明します。
- 事前準備
- 税理士事務所価値の算定
- 買い手探し
- 交渉・基本合意・デューデリジェンス
- 契約締結・PMI
事前準備|資料整理と業務改善を行う
税理士事務所のM&Aによる売却を決断した初期段階では、買い手に開示することになる資料を整理し準備することが肝要です。
M&Aにおける基本的な開示資料としては、中期事業計画書、財務諸表、顧問契約一覧、従業員情報、業務マニュアルが該当します。
また、M&A交渉において買い手から収益性や効率性の高い税理士事務所として評価を得るために、無駄なコストの見直し、会計ソフト導入や業務フローのDX化をこの時期に行っておくべきです。
短期間での業務改善は困難であるため、理想的にはM&Aの1〜2年前から計画的に取り組みましょう。
| 項目 | 内容 | 目的・ポイント |
|---|---|---|
| 中期事業計画書 | 3~5年程度の事業計画書を作成する | 買い手に今後の事業見通しを示す |
| 顧問契約一覧 | 顧問先名、契約内容、年額報酬、契約期間などを一覧化 | 中期事業計画の根拠となり、事務所価値に直結 |
| 人員体制の明確化 | 従業員構成、担当クライアント、雇用形態などを把握 | M&A後の運営体制や人件費の見通しが立つ |
| 業務マニュアルの整備 | 業務フロー、使用ソフト、引継ぎポイントなどを文書化 | 引継ぎの円滑化、属人化リスクの低減に効果 |
| 業務改善・DX対応 | ペーパーレス化、クラウド会計ソフト導入、冗長コスト削減など | 効率化による利益率改善は、評価額向上に直結 |
| 準備開始のタイミング | M&Aの1〜2年前が理想 | 十分な準備期間があると、売却条件や相手選定の自由度が高まる |

M&Aにおける準備不足は「評価額の低下」や「買い手からの信頼毀損」に直結するため、早期の着手が重要です。
税理士事務所価値算定|売却価格の相場を把握する
税理士事務所のM&Aにおいては、初期段階で事務所価値を客観的に把握することが重要です。
税理士事務所のM&Aでは、一般的な企業価値評価方法に加え、業界特有の要因を考慮した評価が求められます。
| 評価要因 | 具体的な内容 |
|---|---|
| 地域特性 | 都市部・地方の違い |
| 対象税理士事務所の特性 | 顧問先の個人・法人比率、業種構成、平均顧問料水準 |
| 人的要因 | 従業職員の定着率、経営者の業務、関与度合い |
| 市場比較 | 同類案件との比較 |
税理士事務所特有の評価要因や、地域・業界における直近の成約事例を適切に評価するには、税理士事務所M&Aに豊富な実績を持つ仲介会社の知見が不可欠です。
専門仲介会社への依頼が必要な理由

適切な企業価値評価に基づく希望売却価格の設定により、交渉時の判断基準が明確になり、M&A成功の可能性が高まります。
買い手探し|M&A仲介会社を通じてマッチングする
M&A仲介会社に業務委託した場合、買い手候補探しはM&A仲介会社の業務です。
M&A仲介会社は、売り手側の希望条件(価格、引継ぎ体制、地域など)に基づき、買い手候補となる税理士事務所や個人の税理士をリスト化します。
マッチングは、「リストから3~4候補に絞り込み→優先度をつけた順にM&A仲介会社が交渉を打診→合意相手と秘密保持契約(NDA)」という流れです。
| 買い手候補の種類 | M&Aの狙い | 検討時のポイント |
|---|---|---|
| 未開業の個人税理士 | 事業譲渡で税理士事務所を開設持分譲渡で税理士法人の経営陣 | 自身の経営適性を判断 |
| 税理士事務所 | 事業譲渡で事業拡大 | 個人経営の継続か法人化するか |
| 税理士法人 | 事業譲渡、合併で事業拡大合併で拠点拡張 | 経営統合の見通し |

税理士事務所のM&Aにおける買い手とのマッチングでは、妥協せず条件の一致する相手を選びましょう
交渉・基本合意・デューデリジェンス|条件調整と買い手側によるリスク確認
譲受側は、M&Aの実行前に実施するデューデリジェンス(DD)において、税務・財務・法務の観点からリスクを詳細に調査します。
簿外債務、過去の税務申告、契約関係の不備が確認された場合には、譲渡価格の見直しや条件変更に直結する可能性があります。
また、条件交渉では「価格」だけでなく、「顧問契約の引継ぎ」「職員の処遇」「譲渡側代表者の退任後の関与可否」など、実務面に関する合意形成も不可欠です。
トラブル防止のためにも、専門家の助言を得ながら客観的・中立的に交渉を進めましょう。
| 項目 | 内容・確認ポイント | 補足 |
|---|---|---|
| 引継ぎ条件の交渉 | 顧問先対応、従業員の雇用継続、譲渡側経営者の関与期間など | 価格以外の実務的な条件の詳細確認が必要 |
| 財務デューデリジェンス | 売上の推移、利益率、貸借対照表の整合性など | 財務資料の提出と収益変動・債務状況の説明が必要 |
| 税務デューデリジェンス | 過去の税務申告内容、未納税・過少申告の有無 | 直近数年分の税務申告書類提出とリスク開示が必要 |
| 法務デューデリジェンス | 契約書の不備、係争リスク、知的財産や商標の整理状況など | 各種契約書類の提出と引継ぎ可否の回答が必要 |

M&Aのデューデリジェンスにおいては、売り手は買い手の求めに応じ、資料提供やインタビュー対応など建設的に協力しなければなりません。
契約締結とPMI|M&A成約後は買い手による統合プロセスが行われる
デューデリジェンスの結果を基に最終交渉が行われ、条件面で双方が合意に達すれば最終契約を締結します。
ただし、デューデリジェンスで重大なリスクが発見された場合、基本合意の条件変更や破談となる可能性もあります。
契約の締結からクロージングまでの流れは、以下のとおりです。
| 段階 | 内容 | 注意点 |
|---|---|---|
| 最終交渉 | デューデリジェンス結果を基に条件交渉 | 重大リスク発見時は条件変更・破談の可能性あり |
| 最終契約締結 | 双方合意に基づく契約書締結 | 法的拘束力が発生 |
| クロージング | 資産引き渡しと対価受け取り | M&A効力発生のタイミング |
クロージング後、以下のケースでPMIへの協力が必要になります。
協力が求められるケース
主な協力内容

PMI計画の策定はデューデリジェンスの実施と並行して進められるため、売り手はこの段階から買い手と綿密に情報を共有する必要があります。
まとめ|相場を理解して、最適なM&Aを実現しよう
税理士事務所におけるM&Aを成功させるには、相場やM&Aスキームを正しく理解することが大切です。
以下のポイントを押さえることで、納得のいく取引につながります。
税理士事務所のM&Aにおける売り手側としては、上記のような前提を踏まえ、M&A実施の1〜2年前から準備を開始することで、評価額の最大化が期待されます。

税理士事務所のM&Aを検討するにあたっては、信頼できるM&A仲介会社探しから始めましょう。各社が実施している無料相談を有効活用することをおすすめします。
\ 相談料も着手金も無料、まずはお気軽にご相談ください。/
ご相談いただいた内容は、秘密厳守で丁寧に対応させていただきます。