なぜ税理士業界は人手不足が止まらないのか?現状と解決策を解説
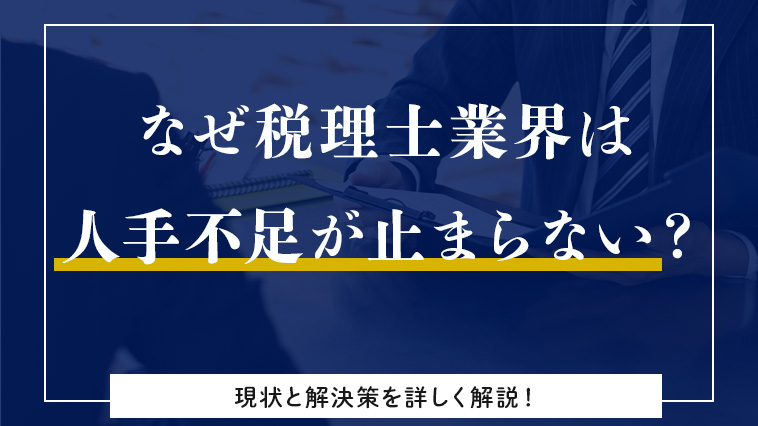
税理士業界では現在、人手不足が深刻な課題となっています。
背景には、高齢化、若手人材の不足、業務量の増加、労働環境とのミスマッチなど、複数の要因が複雑に関係し合っています。
また、有効求人倍率は約2.3倍と、他業種に比べて高い水準にあり、人材不足が慢性化していることが数値からも明らかです。
人手不足の影響は、事務所運営の停滞や顧客対応力の低下を招き、経営に直接的なリスクを及ぼしています。
本記事では、税理士業界における人手不足の現状、解決策、M&Aを含めた今後の選択肢について解説します。
記事の結論
税理士業界における人手不足の現状
税理士業界が慢性的な人手不足に直面している背景には、高齢化、若手人材の不足、業務量の増加、求人市場での競争、労働環境の課題など、複数の要因があります。
これらの要因を詳しく分析するため、次の内容について解説します。
- 高齢化で世代交代が進まず若手人材が不足
- インボイス制度や副業増加などの需要拡大で業務量が増加
- 有効求人倍率は約2.3倍(令和6年度)と圧倒的な売り手市場
高齢化で世代交代が進まず若手人材が不足
税理士業界では年齢層の偏りが顕著で、高齢化が進んでいるのが現状です。
若手の割合が低く、世代交代が進まないという課題が明らかになっています。
日本税理士会連合会の調査によると、登録税理士のうち、20代と30代は合わせて10.9%にとどまる一方で、50代以上が71.6%を占めており、年齢構成に大きな偏りがあります。
このように、50代以上が7割を超える年齢構成は、業界全体の柔軟性や将来性を損なう要因です。
以下に、税理士の年齢層構成を整理しました。
| 年齢層 | 割合 |
|---|---|
| 20代 | 0.6% |
| 30代 | 10.3% |
| 40代 | 17.1% |
| 50代 | 17.8% |
| 60代 | 30.1% |
| 70代 | 13.3% |
| 80代 | 10.4% |
参考:日本税理士会連合会実施 第6回税理士実態調査結果 ※割合合計が100%になりませんが資料どおりに転載しています。
上記のデータを見ると、20代は1%未満、30代も1割程度と、若年層が極端に少ないです。
若手人材の不足は、デジタル技術や柔軟な働き方への適応力を弱めるだけでなく、業界全体に「変化に弱い」という印象を与える要因となっています。
その結果、他の専門職と比べて職業としての魅力が低下し、人材が集まりにくい状況が続いています。
このような人材構成の偏りは、採用、育成、事業承継のすべてに悪影響を及ぼしており、税理士業界にとって解決すべき課題です。
インボイス制度や副業増加などの需要拡大で業務量が増加
税理士業界では近年、複雑かつ多様な業務を慢性的に抱える状況が続き、現場の負担が深刻化しています。
背景には、税制度改正(インボイス制度や頻繁な税制改正)や社会構造の変化(副業人口の増加や電子申告の普及)があり、対応すべき業務の範囲が急速に広がっています。
以下に、業務量を押し上げている要因を整理しました。
| 要因 | 内容 |
|---|---|
| インボイス制度導入 | 適格請求書発行事業者登録支援、新経理システム導入サポートなど新規業務が発生 |
| 副業人口の増加 | 確定申告件数の増大、個人事業主・フリーランス対応による業務の増加 |
| 頻繁な税制改正 | 法改正に伴う勉強会の実施、顧客への説明、実務処理の見直し |
| 電子申告の普及 | システム対応、新規トラブル対応、顧客サポート業務の追加 |
いずれも、新しい知識の習得や追加業務への対応を職員に求めるものであり、少人数の事務所では負担が急増する要因です。
その結果、限られた人員で対応する税理士事務所には、大きな負担がかかっています。
年末調整、確定申告、法人決算といった繁忙期に業務が集中することで、長時間労働や対応遅延が常態化しやすく、人材不足の深刻化や離職リスクの高まりにつながっています。
有効求人倍率は約2.3倍(令和6年度)と圧倒的な売り手市場
税理士の求人市場は、求人が応募者数を大きく上回る状況にあり、極めて売り手側に有利です。
令和6年度時点の有効求人倍率は2.31倍であり、全産業平均の1.25倍を大きく上回る水準です(参考:厚生労働省「job tag」、厚生労働省「一般職業紹介状況」)。
この数値は「求人数は多いが応募者が少ない」という深刻なミスマッチを示しており、完全に売り手市場であることを示しています。
有効求人倍率の高さを生む要因は次のとおりです。
| 要因 | 内容 |
|---|---|
| 専門資格の必要性 | 税理士は国家資格であり、候補者そのものが限られている |
| 業務の需要増加 | インボイス制度や副業人口増加により税務サービス需要が拡大 |
| 定着率の低さ | 長時間労働や繁忙期負担が敬遠され、人材の流出が続く |
資格の希少性、業務需要の拡大、定着率の低さが重なり、採用市場は慢性的にひっ迫しています。
都市部の大手事務所に人材が集中する傾向が強く、中小規模や地方の事務所では応募者が集まりにくく、採用環境は一層厳しい状況です。
給与水準や福利厚生の改善といった「採用コストの上昇」が避けられず、特に中小や地方の事務所にとって大きな経営負担となっています。
税理士の人手不足がもたらす悪影響
税理士業界における人手不足は、単なる業務の多忙にとどまらず、事務所の運営やサービス品質に深刻な影響を及ぼしています。
具体的には、繁忙期の長時間労働による疲弊、顧客対応の遅れ、DX推進の停滞などです。
ここからは、以下の内容について詳しく解説します。
- 繁忙期の長時間労働がミスと疲弊を生む
- 顧客対応の遅れで信頼が失われる
- DX推進の遅れが競争力低下を招く
繁忙期の長時間労働がミスと疲弊を生む
税理士事務所では、年末調整、確定申告、法人決算などの業務が集中する繁忙期(11月から翌年5月頃)に、通常期を大きく上回る業務量を抱えることになります。
限られた人員で対応せざるを得ず、長時間労働が常態化し、職員一人あたりの負担が増大します。
主な悪影響を整理すると次のとおりです。
| 繁忙期の要因 | 現場への影響 |
|---|---|
| 年末調整・確定申告・決算の集中 | 通常期を大きく上回る業務量が発生し、長時間労働が常態化する |
| 少人数体制での対応 | 1人あたりの担当件数が増加し、心身の疲労が蓄積する |
| 短期間での処理要求 | ミスや確認不足が発生しやすく、顧客対応の質が低下する |
疲労の蓄積は業務効率を低下させ、計算ミスや書類不備のリスクを高めます。
特に深刻なのは、この過重労働が人材不足を加速させる悪循環を招くことです。
この悪循環が繰り返されることで、離職増加に伴う採用難や顧客対応力の低下といった実務上のリスクが高まり、税理士事務所の信頼性や持続性に深刻な影響を及ぼします。
顧客対応の遅れで信頼が失われる
人手不足によって職員の業務量が増えると、顧客対応が遅れやすくなります。
問い合わせへの返答や成果物の納品が遅れるだけでなく、新規案件への着手が滞るなど、日常業務に支障が生じやすくなるでしょう。
以下に、顧客対応の遅れが具体的にどのような影響を及ぼすのかを整理しました。
| 顧客対応の遅れの事例 | 影響 |
|---|---|
| 問い合わせへの返答遅延 | 顧客の不安を招き、満足度が低下する |
| 成果物納期の遅延 | 顧客の業務や資金繰りに支障を与える |
| 新規案件対応の停滞 | 顧客が他の事務所へ流れるリスクが高まる |
これらはいずれも顧客満足度を低下させ、最終的には事務所の信頼や評判を損なう要因です。
税理士業務は顧客との信頼関係を基盤としているため、一度信頼を失えば、その回復には長い時間と多大な労力を要します。
信頼が失われて顧客が離れれば、収益の減少や顧客基盤の縮小など、経営面に深刻な影響を及ぼすおそれがあります。
DX推進の遅れが競争力低下を招く
人手不足により日々の業務対応に追われる税理士事務所では、新しいシステム導入や業務改善に充てる時間を確保できません。
その結果、DXの取り組みが後回しとなり、クラウド会計、RPA(Robotic Process Automation)、AI活用などの導入が遅れる状況に陥ります。
| 事例 | 影響 |
|---|---|
| クラウド会計導入の遅れ | 業務効率化が進まず、入力に時間がかかり生産性が低下する |
| RPA(自動化)の導入不足 | 定型業務が人手依存のままで、負担が減らない |
| AI活用の遅れ | データ分析や予測ができず、付加価値提供が制限される |
効率化が進まなければ生産性が向上せず、他の事務所との競争において不利となる要因です。
また、デジタル化の遅れは、リアルタイムの経営数値提供や迅速な税務相談対応など、顧客サービスの質にも影響します。
IT活用に積極的な事務所との差が拡大すれば、顧客獲得や人材採用において競争力を失うリスクが高まります。
DX推進の停滞は、短期的な効率化の遅れにとどまらず、長期的には税理士事務所の存続に直結する重要な課題です。
人手不足を解消するための具体策
税理士業界の人手不足は深刻な課題ですが、解決の糸口は複数存在します。
採用と育成の工夫、働き方改革による定着促進、IT活用による効率化、外部人材の登用など、複数のアプローチがあります。
現状は厳しいものの、これらを組み合わせて取り組めば、人手不足の緩和が可能です。
ここでは、次の具体策を順に整理して解説していきます。
- 採用や人材育成を工夫する
- 働き方改革を行い職場環境改善に努める
- RPAやAIで定型業務を自動化
- 繁忙期は外部人材を活用して負担を分散する
採用や人材育成を工夫する
税理士事務所の人手不足を解消するには、経験者に限らない幅広い人材の採用と、採用後の体系的な育成が不可欠です。
採用の間口を広げて担い手を確保し、育成によって定着と成長を促すことで、長期的に安定した人材基盤を整えられます。
| 取り組み領域 | 具体策 |
|---|---|
| 採用の工夫 | ・未経験者やポテンシャル層の積極採用 ・意欲ある人材を幅広く受け入れる ・シニア層や復職希望者の活用 |
| 育成の強化 | ・明確なキャリアパスの提示による成長支援 ・資格取得支援制度の導入 ・OJTや研修の充実 |
これらの施策は、人材を「採用して終わり」にせず、長期的に活躍してもらうための仕組みづくりにつながります。
育成に力を入れることは、短期的にはコストを要するものの、人材の定着率を高め、事務所の持続的な競争力を支える投資です。
採用と育成を両輪で進めることが、人手不足の根本的な解消と、税理士事務所の成長基盤の確立に結び付きます。
働き方改革を行い職場環境改善に努める
税理士事務所において人材が定着しにくい背景には、長時間労働や休暇の取得の難しさがあります。
このような職場環境を改善するには、働き方改革を進め、業務負担を軽減しながら、働きやすさと成長機会を両立させることが重要です。
| 具体策 | 期待される効果 |
|---|---|
| リモートワーク・フレックスタイム導入 | 柔軟な働き方を実現し、ワークライフバランスを改善できる |
| 残業時間の削減 | 過重労働を防ぎ、疲労を軽減できる |
| 有給休暇取得の促進 | リフレッシュ機会を確保し、定着率を高める |
| 明確なキャリアパスの提示 | 将来の見通しを示し、モチベーションを高める |
| 評価制度・教育制度の整備 | 公正な評価と成長機会を提供し、意欲を高める |
これらの取り組みによって、「ワークライフバランスの改善 → 離職率の低下 → 採用力の向上」という好循環が生まれることを期待できます。
短期的には制度導入や仕組みの整備にコストを要しますが、定着率の改善や採用コストの削減、生産性の向上といった効果により、中長期的には事務所経営の安定と成長に結び付きます。
RPAやAIで定型業務を自動化
日々の定型業務に多くの時間を費やすと、人手不足はさらに深刻化します。
有効な解決策は、RPAやAIを活用した自動化です。
RPAは繰り返し作業を自動処理し、AIは学習や分析を通じて業務を高度化する役割を果たします。
| 自動化できる業務 | 期待される効果 |
|---|---|
| 会計ソフトへのデータ転記 | 入力ミスを削減し、作業時間を短縮できる |
| 給与計算・経費精算 | ルーティン業務を効率化し、残業を削減できる |
| 税務申告書・届出書の作成 | 書類作成を自動化し、繁忙期の負担を軽減できる |
| 電子申告の処理 | 提出を自動化し、期限遅延や誤送信を防げる |
| AIによる仕訳判定・経営分析 | 単純作業を削減し、顧客への提案に活用できる |
導入によって、効率性(時間短縮)、正確性(ミス削減)、負担軽減(残業・繁忙期対策)が実現します。
職員は単純作業から解放され、コンサルティングや顧客対応などの付加価値業務に集中できます。
初期投資は必要ですが、効果は大きく、短期間での投資回収が可能です。
生産性の向上に加え、顧客サービスの質の向上や職員のモチベーション維持にもつながり、事務所の競争力を高める有効な解決策です。
繁忙期は外部人材を活用して負担を分散する
税理士事務所では、繁忙期に業務が集中し、常勤職員だけでの対応には限界があります。
このため、外部人材の活用が有効な解決策です。
短期間であっても専門性を持つ職員を活用することで、即戦力として機能し、既存職員の負担を軽減できます。
| 外部人材の種類 | 活用効果 |
|---|---|
| パート・アルバイトの短期雇用 | 書類整理やデータ入力を担い、既存職員の負担を分散できる |
| フリーランス税理士・会計職員との契約 | 専門知識を持つ人材を即戦力として活用し、業務精度を高められる |
| アウトソーシングサービスの利用 | 記帳や申告業務を外部に委託し、顧客対応に集中できる |
外部人材を活用することで、過重労働の防止、ミスの削減、顧客対応遅延の回避といった効果が期待できます。
固定費を抑えつつ必要な時期に人材を確保できるため、コスト面でも柔軟に対応できます。
繁忙期における外部人材の活用は、業務負荷を平準化し、既存職員の健康管理と顧客サービスの質を維持する有効な取り組みです。
将来の選択肢として考える税理士事務所M&A
人手不足が慢性化する税理士業界では、採用や働き方改革に加え、中長期的な解決策としてM&A(事務所の統合・承継)が注目されています。
M&Aを活用すれば、人材・顧客・ノウハウを同時に獲得でき、採用や育成では補いにくい人材不足の解決が可能です。
後継者不在の税理士事務所が増えるなか、承継型のM&Aは譲渡側にとって事業継続の道を開き、譲受側にとっては人材確保と事業拡大を同時に実現できる点がメリットです。
ここでは次のテーマを掘り下げて解説します。
- 人材・顧客・ノウハウをまとめて得られるM&Aの強み
- 後継者不在の事務所承継で人材確保と事業拡大を両立
人材・顧客・ノウハウをまとめて得られるM&Aの強み
採用や育成には時間とコストを要しますが、M&Aの譲受側であれば即戦力の人材を含む税理士事務所の資産を一括して引継ぐことが可能です。
業務に習熟した職員を承継できるため、採用や育成に伴う負担を大幅に削減できます。
顧客基盤や業務ノウハウも同時に承継できるため、売上の安定やサービス品質の向上につながります。
メリット
M&Aは、人材・顧客・ノウハウを一括で獲得できる点において採用活動とは異なる強みを持ち、人材不足の解消と税理士事務所の持続的な成長を両立できます。
M&Aにより事業承継問題の解決・人材確保・事業拡大を両立
所長が高齢で後継者がいない税理士事務所にとって、事業の承継と事務所の存続は、早急に対応すべき重要な課題です。
その解決策として、M&Aは有効な手段です。
有望な買い手に事務所を引継ぐことで廃業を回避でき、職員の雇用が守られ、顧客も継続してサービスを受けられます。
一方、譲受側は人材と顧客を一度に確保できるため、双方にとってメリットがあります。
| 立場 | メリット |
|---|---|
| 譲渡側 (後継者不在の税理士事務所) | 事業譲渡・合併で職員・顧客の立場を維持 持分譲渡で事務所存続 |
| 譲受側 | 即戦力をまとめて一気に獲得 顧客継承により事業規模拡大 |
M&Aは、事業譲渡、持分譲渡、合併など複数のスキームから、税理士事務所の状況に応じて最適な方法を選べる点も特徴です。
後継者不在の解決とM&Aによる事業拡大は、譲渡側には安心を、譲受側には成長の機会をもたらし、事務所の経営と業界全体の発展を同時に支える有効な選択肢といえます。
人材不足をチャンスに変えるために今できること
人材不足は深刻な課題である一方で、税理士事務所を変革し、成長させる大きなチャンスでもあります。
人材不足を解決するための具体的な取り組みは、次の5つです。
これらの取り組みは、人材不足を補うにとどまらず、税理士事務所の持続的な成長を後押しします。
人材不足という厳しい状況を前向きに活かすことで、顧客から一層信頼される事務所づくりにつながります。
まずは、自事務所の現状に合った取り組みを1つ選んで、始めてみてはいかがでしょうか。
\ 相談料も着手金も無料、まずはお気軽にご相談ください。/
ご相談いただいた内容は、秘密厳守で丁寧に対応させていただきます。